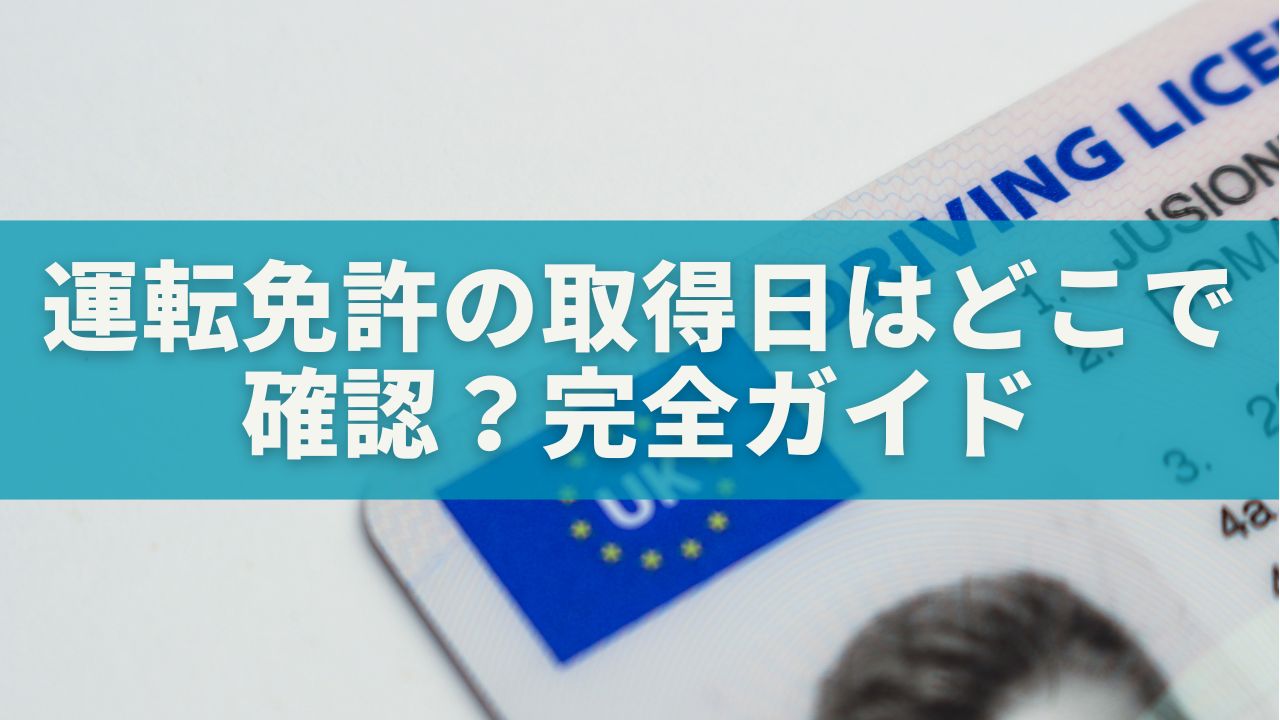履歴書や自動車保険の手続きなどで、「運転免許の取得日」が必要になる場面は意外と多いですよね。
しかし、いざ免許証を見ても「どこに書いてあるの?」「交付日と違うの?」と迷ってしまう人が少なくありません。
この記事では、免許証を見てすぐに分かる取得日の確認方法から、複数免許の正しい調べ方、そして混同されやすい「交付日」との違いまでを分かりやすく整理しました。
また、履歴書での正式な書き方や、取得日によって変わる運転できる車の範囲も詳しく紹介。
この記事を読めば、あなたの運転免許情報を正確に把握し、どんな書類にも自信を持って記載できるようになります。
運転免許の取得日はどこで確認できる?
「運転免許の取得日」は、免許証のどこを見れば分かるのでしょうか。
実は、免許証の左下にある3つの日付欄を見れば、誰でも簡単に確認できます。
ここでは、その見方と仕組みを分かりやすく解説します。
まずは免許証の左下をチェック
運転免許証の左下には、3つの日付が並んでいます。
これは、それぞれ異なる種類の免許を「初めて取得した日」を示しています。
つまり、ここがあなたの免許取得日を確認するための重要ポイントです。
| 欄の名称 | 意味 |
|---|---|
| 二・小・原 | 二輪・小型特殊・原付免許の初取得日 |
| 他 | 普通・中型・大型など第一種免許の初取得日 |
| 二種 | タクシーやバスなどの第二種免許の初取得日 |
例えば、普通自動車免許を最初に取った人は「他」の欄を見ればOKです。
一方で、原付免許を先に取得していた場合は「二・小・原」に日付が入っています。
取得した順番によって、記載される欄が異なることを覚えておきましょう。
「二・小・原」「他」「二種」3つの欄の意味を理解しよう
この3つの欄は、単に「免許の種類」ではなく、「どのグループの運転資格を最初に得たか」を示す仕組みです。
たとえば、原付→普通免許→大型免許の順に取得した場合、免許証には以下のように表示されます。
| 欄 | 記載内容 |
|---|---|
| 二・小・原 | 原付を取得した日 |
| 他 | 普通免許を取得した日 |
| 二種 | 空欄(取得なし) |
つまり、普通免許を知りたいなら「他」、二輪免許を知りたいなら「二・小・原」を見れば十分です。
間違えて右上の「交付日」を見ないように注意しましょう。
「取得日」と「交付日」はどう違う?履歴書に書くのはどっち?
免許証には「取得日」とは別に「交付日」という日付もあります。
見た目が似ているため混同されがちですが、実はまったく意味が異なります。
「取得日」は資格を得た日、「交付日」はカード発行日
「取得日」とは、その免許区分(例:普通免許)を初めて取得した日のことです。
一方で「交付日」は、免許証というカードそのものが発行された日を指します。
| 項目 | 意味 | 変わるか? |
|---|---|---|
| 取得日 | その免許を初めて取った日(資格を得た日) | 変わらない |
| 交付日 | 免許証のカードが発行された日 | 更新のたびに変わる |
たとえば、5年前に普通免許を取得し、今年更新した場合。
「取得日」は5年前のままですが、「交付日」は今年の更新日になります。
履歴書や保険書類に記載すべきなのは『取得日』です。
誤って交付日を書くとどうなる?正しい記載方法を紹介
もし履歴書に「交付日」を書いてしまうと、採用担当者から「最近免許を取ったばかりなのかな?」と誤解されるおそれがあります。
そのため、正しい書き方を押さえておきましょう。
| 誤りやすい書き方 | 正しい書き方 |
|---|---|
| 普通自動車第一種運転免許(交付日 2024年3月10日) | 普通自動車第一種運転免許(取得日 2019年6月5日) |
このように「取得日」と明記し、免許証の左下「他」の欄に書かれている日付を転記すれば安心です。
交付日=更新日ではない点も忘れずにチェックしましょう。
免許の正式名称と正しい書き方を確認しよう
履歴書や公的書類に免許を記載する際、意外と迷うのが「正式名称」です。
普段は「普通免許」「中型免許」と呼んでいても、正式名称はそれとは少し異なります。
ここでは、なぜ正式名称で書くべきなのか、そして主要な免許の正しい表記を一覧で紹介します。
通称ではなく正式名称で書くべき理由
正式名称を使用する理由は、書類上の信頼性と正確性を担保するためです。
とくに運転業務を伴う仕事では、免許区分が採用判断に関わる場合があります。
正確な名称を使うことで、持っている資格を正しく伝えることができます。
| 通称 | 正式名称 |
|---|---|
| 普通免許 | 普通自動車第一種運転免許 |
| 中型免許 | 中型自動車第一種運転免許 |
| 大型免許 | 大型自動車第一種運転免許 |
| 準中型免許 | 準中型自動車免許 |
| 普通二輪免許 | 普通自動二輪車免許 |
| 大型二輪免許 | 大型自動二輪車免許 |
| 原付免許 | 原動機付自転車免許 |
| 牽引免許 | 牽引自動車第一種運転免許 |
| 普通二種免許 | 普通自動車第二種運転免許 |
履歴書に「普通免許」だけ書いても通じますが、採用担当者に専門知識がない場合、限定条件や免許区分が誤解されることがあります。
特に「準中型」や「中型」など名称が似ている区分は、正式名称で記載するのが安心です。
免許証の『種類』欄に記載されている名称こそが正式名称なので、必ずそこを確認して書きましょう。
複数の免許を持っている場合、すべての取得日を知る方法
原付・普通・中型・大型といった複数の免許を持っている場合、「どの免許をいつ取ったか」が分かりにくくなります。
免許証の左下欄には「グループごとの最初の取得日」しか載っていないため、後から取った免許の日付を確認したい場合は別の方法が必要です。
ここでは、2つの公式な確認手段を紹介します。
方法① ICチップ情報を読み取る
現在の運転免許証にはICチップが埋め込まれており、そこに詳細なデータが保存されています。
ICチップには、免許の種類ごとの正確な取得日がすべて記録されているのです。
| 確認できる場所 | 警察署、運転免許センター、運転免許試験場 |
|---|---|
| 必要なもの | 免許証、2組の暗証番号(4桁×2) |
| 確認方法 | ICカード読み取り端末に免許証をセットし、暗証番号を入力 |
もし暗証番号を忘れてしまった場合でも、窓口で本人確認を行えば再設定が可能です。
一度確認しておくと、次回から取得日を間違えることがなく安心です。
この方法が最も手軽で確実にすべての免許取得日を知る手段です。
方法② 「運転免許経歴証明書」を発行する
もう一つの確実な方法は、「運転免許経歴証明書」を発行してもらうことです。
この書類には、すべての免許の種類と取得年月日が公式に記載されます。
| 申請場所 | 全国の自動車安全運転センター窓口 |
|---|---|
| 手数料 | 800円(2025年10月時点) |
| 発行期間 | 申請から1〜2週間程度(郵送または窓口受け取り) |
注意点として、「運転経歴証明書」と名前の似た別の書類があります。
これは、免許を自主返納した人向けの身分証明書です。
申請時は必ず「運転免許経歴証明書」と明記してください。
公式な記録を残しておきたい場合や、履歴書で過去の免許取得を証明したい場合にも有効です。
取得日によって運転できる車が違うって本当?
実は、運転免許の取得日によって運転できる車の範囲が異なることをご存じでしょうか。
これは、道路交通法が2007年と2017年に改正され、免許区分の基準が変わったためです。
ここでは、あなたの免許がどのタイプに該当するのかを簡単に確認できるように整理します。
2007年・2017年の法改正で変わった免許区分
法改正によって、「普通免許」として取得した人の中にも、実は「中型」や「準中型」として扱われるケースがあります。
以下の表で、自分の免許がどの区分に該当するかをチェックしましょう。
| 取得日 | 免許区分 | 運転できる車の範囲 |
|---|---|---|
| 〜2007年5月31日 | 中型(8t限定) | 車両総重量8t未満まで運転可 |
| 2007年6月1日〜2017年3月11日 | 準中型(5t限定) | 車両総重量5t未満まで運転可 |
| 2017年3月12日以降 | 普通免許 | 車両総重量3.5t未満まで運転可 |
同じ「普通免許」でも、取得時期によって運転できる車が違うのは驚きですよね。
この区分は免許証の「条件等」欄で確認できます。
条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれていれば、あなたは実質的に中型免許保持者です。
「8t限定」「5t限定」などの条件を確認する方法
免許証の表面右下付近にある「免許の条件等」欄を見てみましょう。
そこに「中型車は中型車(8t)に限る」「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されていれば、それがあなたの限定条件です。
| 表示内容 | 意味 |
|---|---|
| 中型車は中型車(8t)に限る | 8t未満まで運転可能(旧普通免許) |
| 準中型車は準中型車(5t)に限る | 5t未満まで運転可能(旧普通免許) |
| 条件欄に記載なし | 現行の普通免許(3.5t未満) |
もし「自分は中型免許なんて取ってないのに?」と思っても、それは制度変更による自動切り替えです。
取得日によって実際の運転範囲が異なるため、仕事で車を運転する人は必ず確認しておきましょう。
履歴書への正しい書き方と注意点
履歴書や職務経歴書に免許を記載する際、見落としがちなポイントがいくつかあります。
特に運送業や営業職など、車を使う仕事に応募する場合は正確な書き方が求められます。
ここでは、誤解されないための記載ルールを紹介します。
運送業などで特に重要な「限定条件」の記載方法
履歴書には、免許証の記載と同じ形式で書くのが最も正確です。
条件が付いている場合、そのまま表記するのが基本です。
| 免許証の表記 | 履歴書への書き方 |
|---|---|
| 普通自動車第一種運転免許 | 普通自動車第一種運転免許 取得(取得日 2018年7月10日) |
| 中型車は中型車(8t)に限る | 普通自動車第一種運転免許 取得(中型車は中型車(8t)に限る) |
特に運送業界では、運転できる車両区分が採用条件に関わる場合があります。
条件まで正確に書くことで、担当者に誤解を与えず正しいスキルを伝えられます。
採用担当者に伝わる免許の書き方のコツ
履歴書で免許を記載する際の基本ルールは次のとおりです。
- 正式名称で記載する(「普通免許」ではなく「普通自動車第一種運転免許」)
- 取得日を正確に記載(免許証左下「他」の欄)
- 限定条件がある場合はそのまま表記
また、運転免許以外の資格と一緒に書く場合は、行を分けて整理すると見やすくなります。
たとえば以下のような書き方がおすすめです。
| 記載例 |
|---|
| 普通自動車第一種運転免許(中型車は中型車(8t)に限る) |
| 大型自動二輪車免許 |
このように正確かつ丁寧に記載することで、採用担当者に「きちんとした印象」を与えることができます。
特に車を扱う職種では、免許情報の正確性が信頼に直結します。
まとめ:運転免許の取得日は「あなたの運転資格の原点」
ここまで、運転免許の取得日を確認する方法や、交付日との違い、履歴書への正しい書き方などを解説してきました。
最後に、この記事の重要ポイントを整理しておきましょう。
この記事のポイントをおさらい
| テーマ | 要点 |
|---|---|
| 取得日の確認方法 | 免許証左下の「他」欄を見る(普通免許の場合) |
| 交付日との違い | 取得日は変わらない/交付日は更新ごとに変わる |
| 正式名称の記載 | 「普通免許」ではなく「普通自動車第一種運転免許」と書く |
| 複数免許の確認 | ICチップまたは「運転免許経歴証明書」で全て確認可能 |
| 法改正による違い | 取得日によって運転できる車の範囲が変わる |
| 履歴書への記載 | 条件欄も含め、免許証通りに正確に書く |
「たかが日付」と思われがちな取得日ですが、実はあなたの運転資格を証明する大切な情報です。
取得日を正しく理解することは、安全運転と信頼の第一歩です。
履歴書や保険の手続きだけでなく、免許制度の仕組みを理解する良い機会にもなります。
今すぐできるチェックリスト
この記事を読んだら、次のステップを確認してみましょう。
- 手元の免許証で左下の日付欄をチェックする
- 「交付日」と間違えていないか確認する
- 正式名称と限定条件をメモしておく
- 複数の免許を持っている人はICチップや経歴証明書を確認
- 履歴書に正確な情報を反映させる
これらを実践するだけで、あなたの免許情報は完璧に整理されます。
免許証は身分証明書であると同時に、あなたの運転キャリアの記録でもあります。
ぜひこの機会に、自分の免許証を改めて見直してみてください。